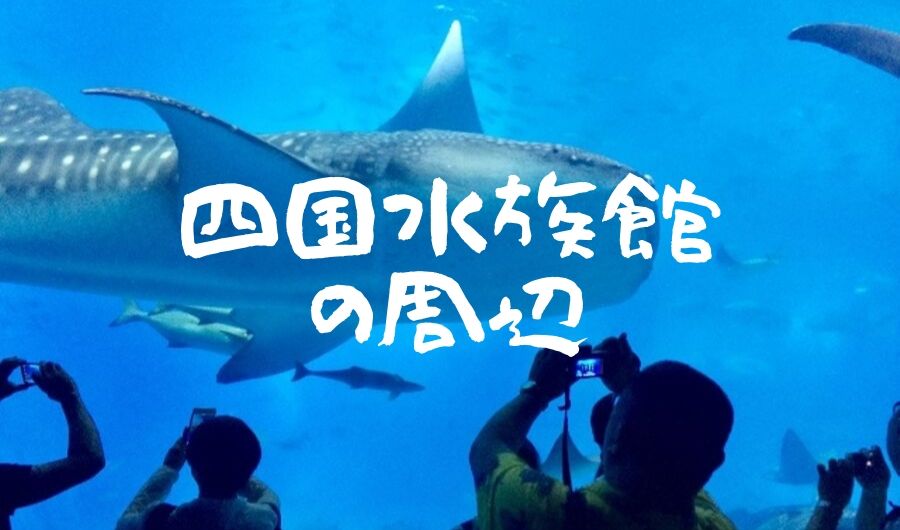はじめに
住宅ローン金利、とても気になります。金利がどう決まるか、突きつめると日本の景気の動向もわかっておもしろいです。
すこしだけ取っ付きにくい話なので、最初に流れを書いておきます。
- 国債って何?
- 国債金利とローン金利は連動する
- 景気対策に日銀の金融緩和
- 金融緩和とは国債の大量買い
- 国債の大量買いで国債金利が下がる
- 国債金利が下がりローン金利も下がる
ざっとこんな感じですが、どうしてそうなるかは本文をご覧ください。
国の借金、その名は「国債」

住宅ローンの金利を知るには、まず日本国債(以下国債)を知る必要があります。
そもそも国債って?
国債とはいわゆる政府の負債です。
日本は長くデフレ(物価が低い)状況が続いています。デフレで景気が悪いので、税収も増えません。国の予算も足りないので、政府は国債の発行を増やしてカバーしています。
その国債の約9割は、国内の銀行や私たち国民が買うことで成り立っています。国の借金1,000兆円超。国民1人当たり、約800万円の借金うんたらの金額です。
私たちや銀行が国債を購入することで、国にお金を貸している。それなのに、私たち『国民の借金』って意味がわかりませんが。
例えば、銀行への預金は私たちの借金でしょうか。答えはNOですね。私たちが銀行にお金を預けている(貸している)だけの、いわば銀行の負債です。それと同じです。
国債のながれ
国債は財務省が発行します。それを金融機関(生命保険会社、損害保険会社、証券会社など)が、入札により購入します。

個人向けには、金融機関の窓口で売られています。そして個人以外には、流通市場※で売買されます。市場での取引ですので、その時々に売買価格と金利が変動します。
※流通市場(シジョウ)とは、発行済の証券が投資家から投資家に流通・売買される市場のことです。流通市場は取引所のように具体的な市場が存在します。住宅ローン金利と国債金利の比較
基本的に、銀行の一般向け住宅ローンの金利は、国債金利に連動しています。
国債金利
国債には償還期間というものがあります。この国債の償還期間ごとの金利が、住宅ローン金利に影響します。
償還期間とは、国債の運用開始日から終了日までの期間のことです。償還期間には以下のものがあり、長いほど金利が高くなります。
| 超長期国債 | 15年、20年、30年、40年 |
| 長期国債 | 10年 |
| 中期国債 | 5年 |
| 短期国債 | 1年 |
住宅ローン金利と国債金利の比較
次のグラフは、住宅ローン(三井住友銀行)と国債の償還期間ごとの金利推移です。
償還期間ごとの金利推移

「住宅ローン金利は、国債金利に連動している」と言えますね。
国債金利と日銀の景気対策
日本銀行(以下、日銀)は銀行の銀行、いわば銀行の親玉です。

景気対策とは
景気が悪い状態が長いため、これまで政策もコロコロ変わりました。政府による財政出動や緊縮財政、日本銀行による金融緩和や金融引締めです。
現政権による、景気回復政策のための政策はアベノミクスですね。
アベノミクス3本の矢
- 財政出動
- 金融緩和
- 成長戦略
このなかで日銀は、②金融緩和の部分を担っています。金融緩和とは、日銀が国債を大量に買いつけるという政策のことです。
日銀の金融緩和は、アベノミクスの実行に必要不可欠な政策です。日銀がおこなっている金融緩和は、景気回復の起爆剤となります。
金融緩和政策による影響
日銀の大規模な金融緩和(国債大量買いつけ)によって、つぎの流れが発生します。
- 日銀による国債の大量買いつけ
- 国債の品薄状態
- 国債の価値が上がる
- 国債金利が下がる

国債が品薄のときは、国債の価値が高まり金利が低くても売れます。逆に、国債が余っているときは、金利を高く付けないと売れません。
ですので、日銀が国債を大量に買いつけるほど、結果的に国債金利は低下します。
国債金利の動向
これは初めに出てきたグラフと同じもので、国債金利の動向となります。


- 2016年1月 マイナス金利導入。金利が爆発的に低下
- 2016年7月 国債金利が過去最低を更新
- 2016年9月 長短金利操作により、2017年以降は横ばい安定
こうして住宅ローン金利が下がる
日銀が金融機関から大量に国債を買いつける。これにより、金融機関の当座預金残高は増加します。

2016年1月、国債の大量買いつけに加え、マイナス金利政策も導入しました。金融機関は、日銀の当座にお金を預ければ、その分だけ赤字となります。
つまり金融機関は、日銀への預金を増やすことを避けなければいけません。金融機関としては、投資や融資(ローン)などを増やす努力を強いられている状況となっています。
結果的に、世の中にお金を回らせることとなります。お金が回る、イコール景気回復を目指した政策です。
そして金融機関の間で競争となり、ローン金利を下げざるを得ない状況となります。つぎの記事では、低金利がいつまで続くかを予測できます。
↓ ↓ ↓